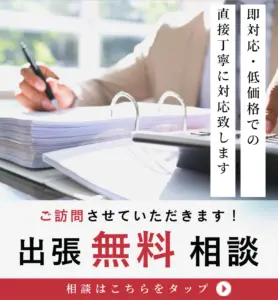お役立ち情報
みなさんこんにちは。 秋田県にある大規模木造建築専門のMOKUPIAです。
「障がい者グループホームの経営に興味があるが、本当に儲かるのだろうか?」「社会貢献と事業性を両立できると聞いたけれど、障がい者グループホームの経営を始めるための具体的な手順やリスクが知りたい」このような、障がい者グループホームの経営に関する疑問や関心をお持ちではないでしょうか。
障がいを持つ方々が地域社会で安心して暮らせる住まいを提供する障がい者グループホームの経営は、非常に社会的意義が深い事業です。同時に、国の制度に基づいた安定的な収益モデルを持つことから、土地活用や新規事業として注目されています。この記事では、障がい者グループホームの経営について、そのビジネスモデルや収益構造、経営のメリットとリスク、そして開業までの具体的な流れと成功のポイントまで、大規模木造建築のプロの視点も交えながら、徹底的に解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、障がい者グループホーム経営の全体像が明確になり、事業を安定的に軌道に乗せるための具体的な知識が身につきます。障がい者福祉の分野で新たな事業や経営を志す方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
障がい者グループホーム経営の基本モデル
障がい者グループホームの経営を理解する第一歩として、まずは「共同生活援助」というサービスと、その収益がどのように成り立っているのかを知る必要があります。
障がい者グループホーム(共同生活援助)とは?
障がい者グループホームとは、正式には「共同生活援助」と呼ばれる障害福祉サービスの一つです。これは、障がいを持つ方々が、専門スタッフによる日常生活上の援助や介護を受けながら、地域の中にある一軒家やアパートなどで共同生活を送るための住まいを提供する事業です。入居者一人ひとりの自立を支援し、家庭的な環境でサポートすることが、この経営の核となります。
障がい者グループホーム経営の収益構造
障がい者グループホームの経営における収益は、主に以下の3つの柱で成り立っています。
- 訓練等給付費(国保連からの入金) 経営収益の大部分(約7~8割)を占めるのが、この「介護給付費」です。これは、事業者が提供する支援サービスの対価として、国民健康保険団体連合会(国保連)から支払われる公的な給付金です。利用者1人あたりの単価が障害支援区分などによって決まっており、この給付費が経営の安定性を支える基盤となります。
- 家賃収入 入居者から徴収する家賃です。多くの障がい者グループホームでは、国の家賃補助制度(補足給付)の上限額(月額1万円)を踏まえ、入居者の負担を軽減する家賃設定にしているケースが一般的です。
- その他の実費負担 入居者が日常生活で実際に使用する水道光熱費、食材料費、日用品費などを実費として徴収します。この部分は事業者の利益(売上)にはなりませんが、施設運営に必要な経費として徴収するものです。
障がい者グループホーム経営は儲かる?収益と費用のシミュレーション
「障がい者グループホームの経営は儲かるのか?」という問いは、多くの方が抱く最大の関心事でしょう。結論から言えば、高い稼働率を維持し、適切なコスト管理を行えば、安定した収益が見込めるビジネスモデルです。
障がい者グループホーム経営の収益モデル(売上)
収益の柱は前述の「訓練等給付費」です。これは「1日あたりの単価 × 入居者数 × 営業日数」で計算されます。さらに、人員を手厚く配置する「人員配置加算」や、専門的な支援を提供する「福祉専門職員配置等加算」などを取得することで、単価を上げることができ、収益向上に直結します。
障がい者グループホーム経営の費用(初期費用と運営費用)
経営を始めるためには、初期費用と継続的にかかる運営費用が必要です。
主な初期費用
- 法人設立費用: 株式会社や合同会社、NPO法人などを設立するための費用(約10万~30万円)。
- 物件取得費用: 建物を新築または購入する場合の費用、賃貸の場合の敷金・礼金など。
- 改修・設備導入費用: スプリンクラーや火災報知器などの消防設備、バリアフリー改修費用。
- 備品購入費用: ベッド、家具、家電、事務用品などの費用。
主な運営費用(ランニングコスト)
- 人件費: 運営費用の中で最も大きな割合(約50~70%)を占めます。管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員などの給与や社会保険料です。
- 家賃: 物件を賃貸する場合の費用。
- 水道光熱費: 入居者が利用する電気、ガス、水道代。
- その他経費: 車両維持費、通信費、消耗品費、修繕費など。
【シミュレーション】経営の年収・利益モデル例
例えば、定員10名(障害支援区分4の方が5名、区分3の方が5名)の障がい者グループホームを経営し、稼働率90%(常時9名入居)、人員配置加算を取得した場合の簡易的なシミュレーションは以下のようになります。
- 年間売上(訓練等給付費 + 家賃収入など): 約2,500万円~3,500万円
- 年間運営費用(人件費、家賃、経費など): 約2,000万円~3,000万円
- 年間営業利益(年収目安): 約300万円~600万円
これはあくまで一例であり、立地や加算の取得状況、人件費の設定によって大きく変動します。
障がい者グループホーム経営のメリットとデメリット(リスク)
安定性が魅力の障がい者グループホーム経営ですが、事業である以上、メリットとデメリットが存在します。
障がい者グループホーム経営の4つのメリット
- 非常に高い社会貢献性 障がい者グループホームの経営は、障がいを持つ方々の自立と地域生活を支える、社会的意義が非常に大きい事業です。入居者やそのご家族から直接感謝されることも多く、経営者が大きなやりがいを感じられる点が最大のメリットです。
- 国の制度に基づく安定した収益 収益の大部分が国保連からの「訓練等給付費」という公的な報酬で賄われるため、景気の変動に左右されにくい、極めて安定したストック型のビジネスモデルです。売上の未回収リスクもほとんどありません。
- 高い需要と低い競合性 障がい者グループホームの数は年々増加していますが、入居を希望する障がい者の数に対して、施設(受け皿)の供給は全国的に不足しているのが現状です。そのため、一度開設すれば高い入居率を維持しやすく、安定した経営が見込めます。
- 土地活用の選択肢となる 必ずしも駅前の好立地である必要はなく、閑静な住宅街など、一般的な賃貸経営には向かない土地でも事業を展開できる可能性があります。既存の戸建て住宅を改修して活用することも可能です。
障がい者グループホーム経営で注意すべき4つのデメリット
- 人材の確保と定着が難しい 障がい者グループホーム経営の最大の課題は「人材」です。専門知識を持つサービス管理責任者や、夜勤も担う世話人・生活支援員の採用と育成、そして定着は容易ではありません。人手不足が常態化すると、サービスの質が低下し、最悪の場合、人員配置基準を満たせず行政処分の対象となるリスクもあります。
- 入居者間・近隣とのトラブル対応 障がい者グループホームは共同生活の場であるため、入居者同士の人間関係のトラブルが発生することがあります。また、施設開設時に、障がい者への偏見から近隣住民の理解が得られず、反対運動などに発展するケースもゼロではありません。
- 初期費用が高額になりがち 事業を始めるためには、物件の取得や改修、備品の購入など、多額の初期費用が必要です。特に、スプリンクラーなどの消防設備やバリアフリー改修には数百万円単位の費用がかかるため、十分な資金調達計画が不可欠です。
- 行政処分による経営悪化のリスク この事業は、障害者総合支援法や指定基準に基づいて運営されます。万が一、人員配置の不足や不正な給付費の請求(不正請求)が発覚した場合、指定取り消しなどの重い行政処分を受け、経営の継続が困難になるリスクがあります。
障がい者グループホーム経営の始め方|開業までの5ステップ
障がい者グループホームの経営を始めるには、入念な準備と行政手続きが必要です。
ステップ1:法人設立と事業計画の策定
障がい者グループホームの経営は、個人では行えません。必ず「株式会社」「合同会社」「NPO法人」「社会福祉法人」などの法人格を取得する必要があります。同時に、「どのような障がいのある方を対象に、どのような支援を提供したいのか」という理念を固め、詳細な事業計画書と収支計画書を作成します。
ステップ2:物件の選定と確保
事業計画に基づき、グループホームとして使用する物件を確保します。既存の戸建てやアパートを賃貸または購入する方法と、新たに土地を購入して新築する方法があります。物件は、後述する設備基準や建築基準法、消防法を満たしている必要があります。
ステップ3:人員の確保(必要な資格)
障がい者グループホームの経営には、法律で定められた人員基準を満たす必要があります。特に重要なのが以下の職種です。
管理者: 事業所全体を管理する責任者。
サービス管理責任者(サビ管): 入居者一人ひとりの個別支援計画を作成・管理する、事業の核となる専門職。実務経験と研修の修了が必要です。
世話人・生活支援員: 食事や入浴、金銭管理などの日常生活のサポートを行うスタッフ。
ステップ4:行政(指定権者)との事前協議
物件や人員の目処が立ったら、事業所を設置する市町村(または都道府県)の障がい福祉担当課(指定権者)と「事前協議」を行います。ここで事業計画や物件の図面などを提示し、法令上の基準を満たしているか、地域のニーズに合っているかなどの指導を受けます。この協議が非常に重要です。
ステップ5:指定申請と事業所の開設
行政との協議を経て、物件の改修や備品の搬入、スタッフの研修など全ての準備が整ったら、正式な「指定申請」の書類を提出します。書類審査と現地確認を経て、問題がなければ「指定通知書」が交付され、晴れて障がい者グループホームの経営を開始できます。
障がい者グループホームの経営を成功させる5つのポイント
障がい者グループホームの経営を安定的に継続させ、収益を上げていくためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ポイント1:高い稼働率(入居率)の維持
経営の安定は、何よりも高い稼働率(入居率)にかかっています。定員10名の施設で1名空室が出るだけで、月の売上が20万~30万円減少することになります。地域の相談支援事業所や病院のソーシャルワーカーと日頃から良好な関係を築き、空室が出た際にすぐ紹介してもらえる体制を作っておくことが重要です。
ポイント2:加算の適切な取得
収益を向上させるためには、基本報酬に上乗せされる「加算」を積極的に取得することが不可欠です。手厚い人員配置(人員配置加算)や、資格を持つ専門職の配置(福祉専門職員配置等加算)、医療的ケアの提供(医療連携体制加算)など、自施設の強みに合わせて加算を取得できる体制を整えましょう。
ポイント3:優秀な人材の確保と定着
経営の質は、スタッフの質で決まります。私が以前、秋田県内で経営コンサルティングを行った事業者様も、当初は採用に苦戦していましたが、給与水準の見直しと研修制度の充実に投資した結果、スタッフの定着率が劇的に改善しました。働きやすい職場環境を整備し、理念を共有できるスタッフを育てることが、結果的にサービスの質を高め、高い入居率と安定した経営に繋がります。
ポイント4:行政・地域との良好な関係構築
障がい者グループホームの経営は、地域社会の中で行う事業です。行政(指定権者)とは定期的に情報交換を行い、法律の改正情報などをいち早くキャッチアップすることが重要です。また、地域の自治会や民生委員などと良好な関係を築き、お祭りなどの地域行事に積極的に参加することで、「地域に開かれた施設」として認知され、近隣トラブルの予防にも繋がります。
ポイント5:【差別化】木造建築による魅力的な施設づくり
数ある施設の中から選ばれるためには、他にはない「魅力」による差別化が必要です。その強力な武器となるのが、私たちMOKUPIAが得意とする「木造建築」による施設づくりです。
鉄骨造やRC造の無機質な建物とは異なり、木造の建物は、木の温もりや香りが感じられる家庭的な空間を創り出します。この「施設の居心地の良さ」は、入居者やそのご家族にとって、施設を選ぶ上で非常に大きな決め手となります。また、木造建築は鉄骨造に比べて建築コストを抑えられるため、初期費用を削減し、経営の早期安定化にも貢献します。
まとめ
障がい者グループホームの経営は、国の制度に支えられた安定性と高い社会貢献性を両立できる、非常にやりがいのある事業です。その成功は、綿密な事業計画と、収益の柱である「加算」、そして事業の質を支える「人材」にかかっています。
そして、入居者に選ばれ、高い稼働率を維持するための「差別化戦略」として、「建物」そのものへの投資は極めて重要です。障がいを持つ方々が日々を過ごす「住まい」として、家庭的な温かみと快適な居住性を提供する木造建築は、障がい者グループホームの理念と最も親和性の高い構造と言えるでしょう。
私たちMOKUPIAは、秋田県で大規模木造建築を専門に手掛けてきました。障がい者グループホームの経営をお考えの際は、初期費用を抑えつつ、入居者から選ばれる魅力的な施設を実現するための建築プランについて、ぜひ一度私たちにご相談ください。

 0187-88-8588
0187-88-8588